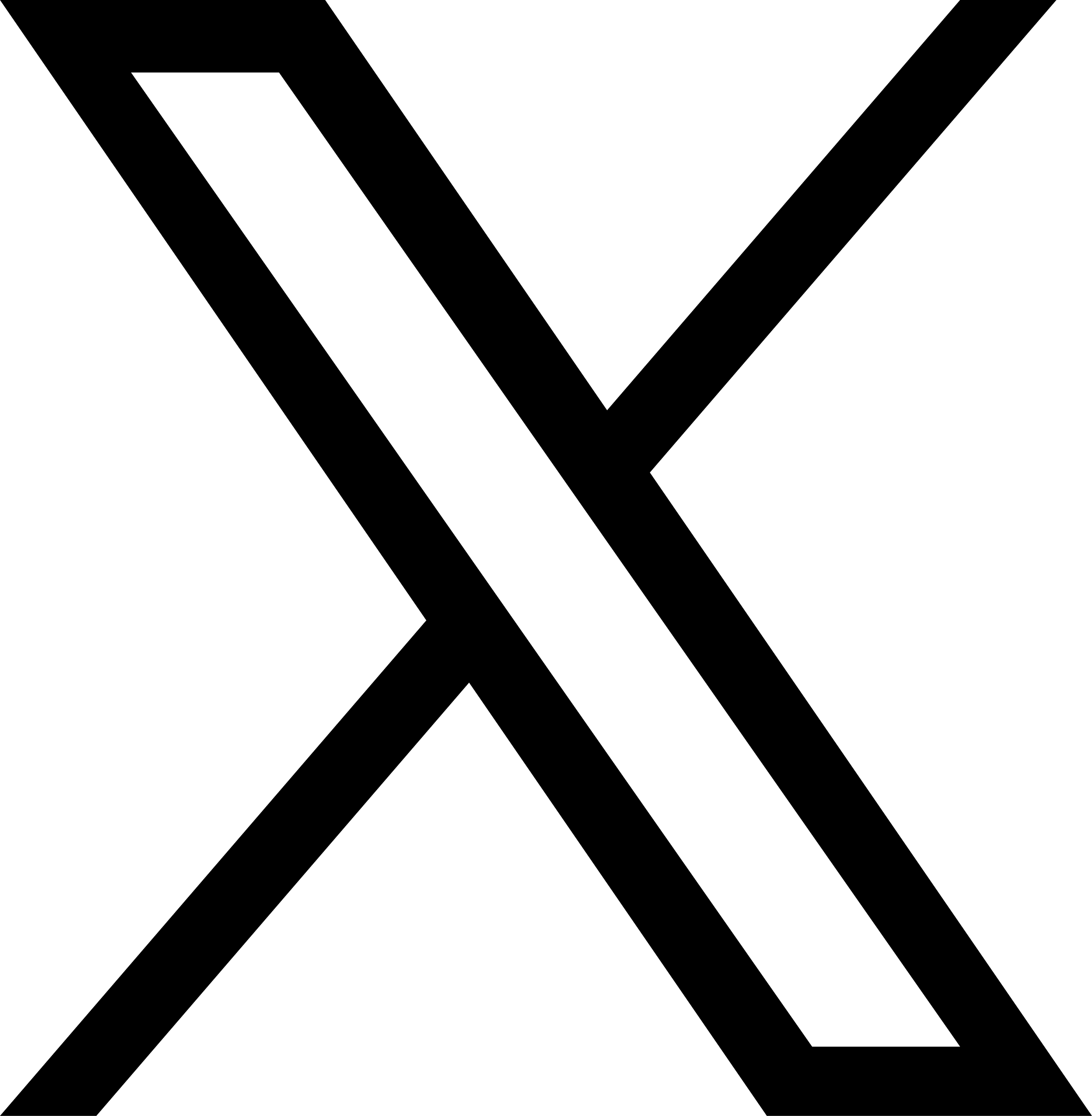建築学科伝統建築領域の大上直樹ゼミは、今年度学部4年生11名と大学院生1名合計12名の構成です。
研究テーマは主に、伝統建築の設計技法、つまり古建築の各部材の寸法がどのような設計原理によって決定されているか?を中心にさまざまなテーマで取り組んでいます。
研究のフィールドは、京都だけでなく奈良や滋賀など関西圏各地の他、徳島県や愛媛県まで建物の実測や調査に出かけています。今回のブログでは、大上ゼミの活動の一部を紹介します。
四国端(はば)八十八箇所の登録文化財の調査研究


これは第1回目の調査で6月に2泊3日で平面図の実測調査を実施しました。卒論の4年生だけでなく、伝統建築領に進む予定をしている2年生も参加していただきました。
8月には第2回目の調査を実施し、10棟の断面図や立面図の実測調査をおこないました。
調査では、棟札の発見もあり、建物の造られた年代や大工名などが判明するなど成果がありました。
棟札の調査研究
棟札とは、棟上げ式などで棟木に打ち付けられる木札で、建立年代、大工など職人の名前などが記されていて、建物の歴史を知る貴重な資料です。
大上ゼミでは、棟札の調査もおこなっていて、8月には野洲市立歴史博物館所蔵の大笹原神社の棟札60数枚の調査をおこないました。

調査は、学生2名、院生1名と教員4名で写真撮影、実測等調書の採取を2日をかけておこないました。
棟札の調査風景
教会堂の調査研究
社寺建築だけでなく、昭和初期に建てられた教会堂などの研究もおこなっています。

楼門建築の設計技法の研究
8月に楼門建築の復原設計をおこなう研究に資するため、4年生3名と中世の楼門が多数残る滋賀県を周りました。

大仏様における黄金比の研究
鎌倉時代に建立された大仏様の建築は黄金比で設計されていた可能性を検討しています。

なお、大上ゼミでは3次元CADやCGを使って研究に役立てています。
4年生が1ヶ月で制作した東大寺開山堂のCG画像
その他、国指定史跡等妙寺遺跡(愛媛県鬼北町)の建築の復原、軒規矩術の研究、仏像と建築の関係、西明寺本堂の当初形式の復原などのテーマを大上ゼミ4年生たちは研究をおこなっています。
(特任教授 大上直樹)