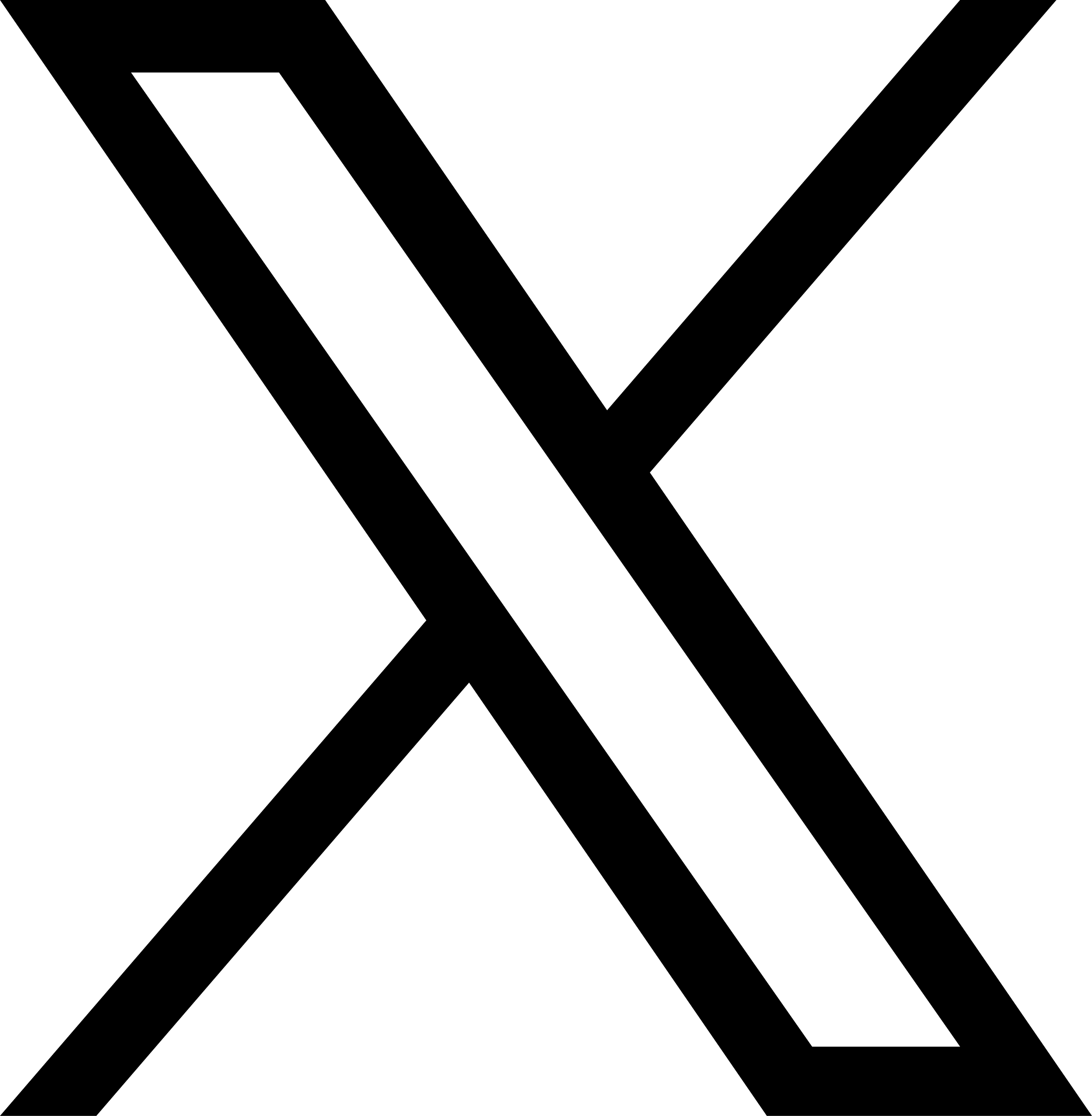建築学科3年生後期の建築デザイン演習Ⅱは、建築デザイン領域と伝統建築領域に分かれます。
伝統建築領域では、大学から徒歩15分ほどの位置にある「新日吉神宮」(いまひえじんぐう)という神社さんで建物の調査をさせていただいています。
新日吉神宮は、平安時代に創立された非常に由緒のある神社です。
ここで実際に調査をさせていただけることは、滅多にない機会で、非常に貴重な体験となります。

調査内容は、
(1)実測調査・・・メジャーなどを用いて野帳(現地で実測したスケッチやメモ書き)を作成する
(2)仕様調査・・・材料や部材の名称、構造など建物の造りを調べる
(3)破損調査・・・建物の傾きや傷んでいる箇所を調べる
となっていて、現地でしかできません。
この調査内容を報告書としてまとめ、最後にはそれぞれの建物の調査内容を発表してもらいます。

調査方法は、建物ごとに班を作って、お互いに協力しながら進めます。
ここでコミュニケーション能力も養われ、お互いの観察力も補完されます。
また、危険行動の監視にもつながり、安全に調査を進められるよう、配慮するようにもなります。

建物のスケッチをするだけとなると簡単そうですが、すべての部材の形状や大きさを把握しないといけませんので、そう簡単ではありません。
じっくりと観察しながら丁寧に野帳を作成していきます。

最初は慣れなかったり、スケッチは得意と思っていた学生さんも、建築の正確な図面を書くとなると少し要領が違います。
しかし、だんだんと慣れ、教員の指導を受けながら進めますので、次第に上達していきます。

現地調査は、天候に左右されますので、雨の日は大学の教室で野帳を整理し、班ごとに進捗やデータを共有し、みんなで相談しながら、効率的に作業を進めていきます。
お互い始めて話す学生さんたち同士も、一つの建物の調査結果をまとめるために、協力するようになっていきます。

建物図面以外にも、例えば石製の手水鉢に刻まれている文字なども調べます。
ここには、「万治三」年(西暦1660年)の年号が見つかり、362年前のものだということがわかりました。
歴史の重みも感じますね。

秋の好天にも恵まれ、順調に作業は進んでいるので、今後の成果が期待されます。
安全に楽しく学び、伝統建築の正しく深い理解に繋げていけたらよいなと考えています。
(准教授 井上年和)