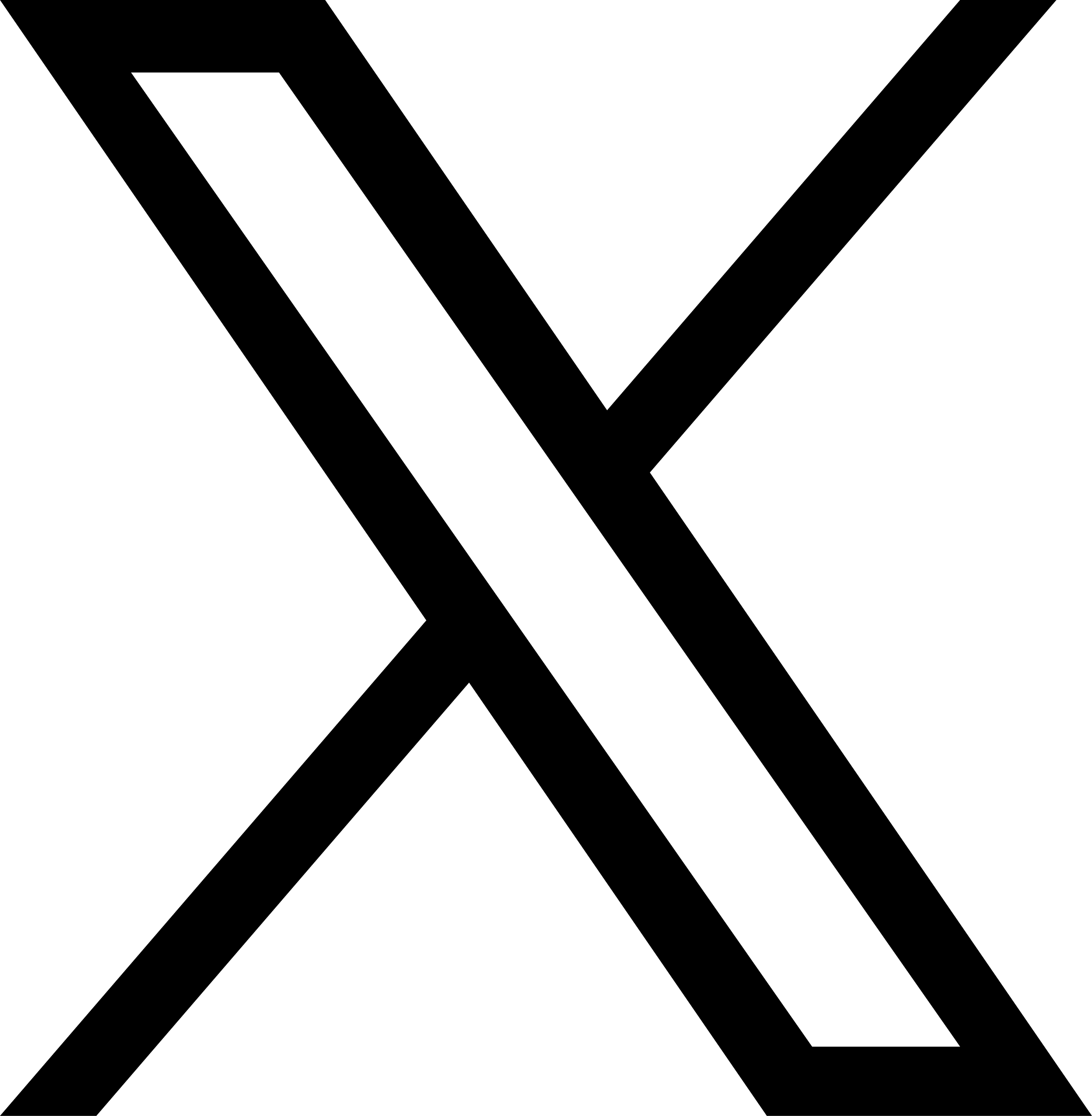こんにちは。建築学科講師の江本です。今回は江本研究室の活動を紹介します。
教員の江本は、近現代建築史を専門とする歴史研究者です。ちかごろは「建築のジャポニスム」研究に熱をあげています(京都新聞)。
本校の卒業制作は「設計」と「論文」の選択制ですが、研究室の6人の学生のうち、半数の3人が論文を志望しています。論文志望者の割合は、他研究室と比較して多いかもしれません。
今年度の江本研の論文志望の学生は、「東京府立美術館の設計と収蔵作品の関係」や、「アメリカの建築理論家の日本受容」、「北欧の人工光デザインの歴史」など、ヒトクセあるテーマを選びました。多様なテーマを見ても分かる通り、学生のテーマ選定は、教員自身の研究と必ずしも関連している必要はありません。共通して肝心なのは、データの集めかたと、まとめかた。そしてデータに差し向ったときの問題発見能力や、疑問を掘りおこすちからです。
そこで今年度は、東京建築旅行を敢行しました。建築旅行とはいえ、その一番の目玉は国立国会図書館です。ここには、日本国内で発行された書籍などが「ほぼすべて」収蔵されています。近年の資料のデジタル化の流れをうけ、ここに行けばとにかく、読みたいものが何でも、すぐ読める……。いわば研究者の聖地のような場所で、学問的調査の敷居をまたぎます。
そこで集められた資料は膨大。決して広くはない館内を何度も往復しながら、熱中して調査にいそしみました。時間の経つのが、とにかく早い。

では、この手元の資料の山をどう料理するか??読みきれるのか?読みきったところで、自分に独自の論文は書けるのか?書くのであったら、資料はまだまだ足りないのではないか???……悩みは尽きません。終わりも見えません。しかし締切は厳然としてある。
まあ、それはそれとして、せっかく東京に来たのだから建築を色々と見てまわります。新宿、上野、芝浦……皆、脚が棒になるほど歩きました。これも何かの発想のきっかけになるとよいです。
(講師 江本弘)