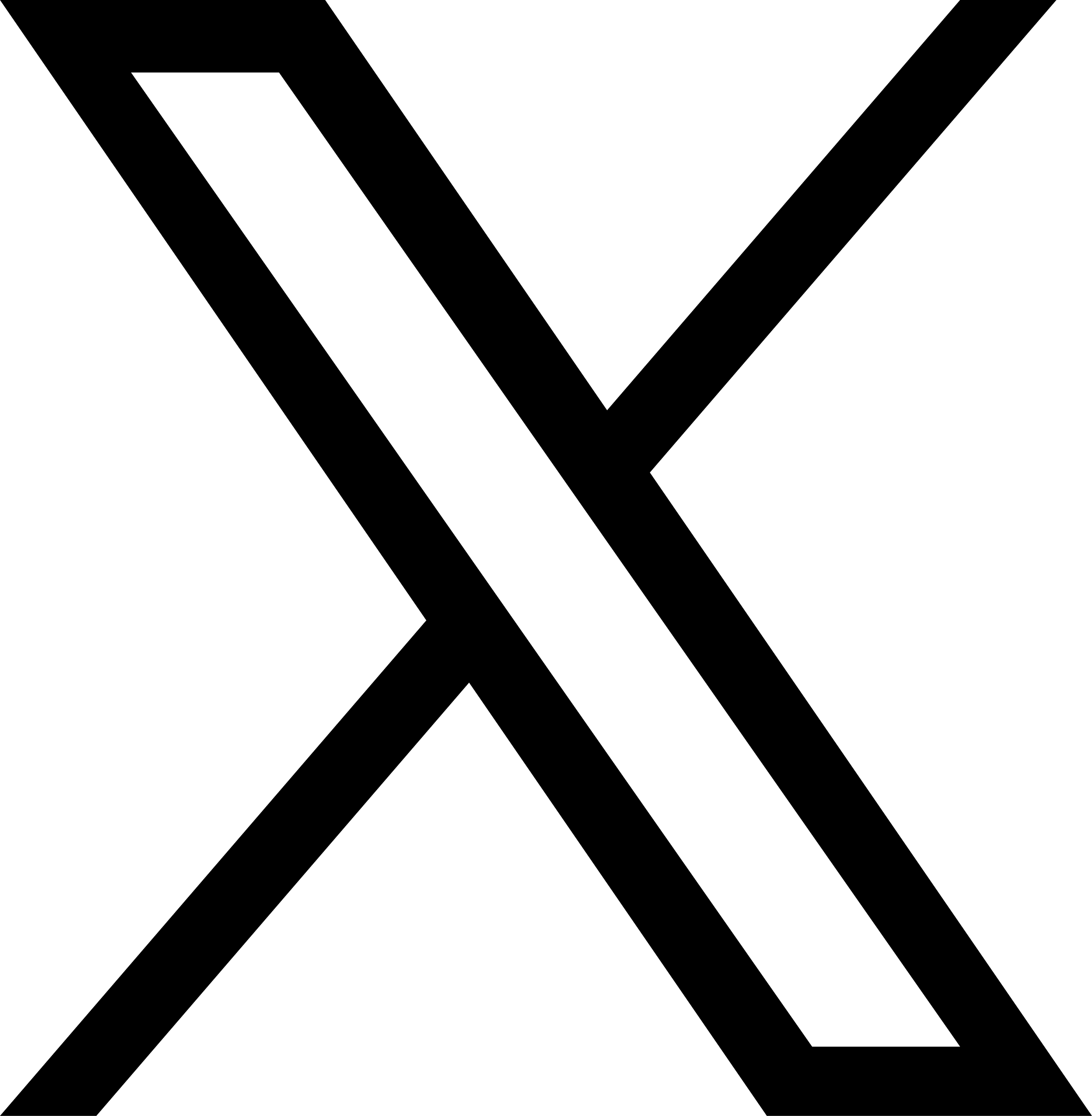この演習では、京都の文化を担うありとあらゆる対象物を「フィールドサーヴェイ」を通じて体感し、学術的に捉えなおすこと基本にします。さらに現地で得た知見を「マップ作成という編集行為」を通じて京都を学問的に見つめる演習です。
京都は、幾重の時代背景をもつ複雑な歴史都市でもあり、現代都市でもあります。その理解は様々な着眼点を基にいくつかの切り口を設定し、対象を客観的に見つめなおし、正確な情報の裏付けがなければ太刀打ちできません。
日頃スマホを片手に京都を歩くと、多くの情報が押し寄せ検索しても知りたい情報にたどり着けず「ネット社会」に翻弄させられます。しかし地図やガイドブックを片手に歩きますと、効率が上がった経験はありませんか。見る目を養えば、京都は地勢と千年を超える事象が高度な文化形態を作り上げた、複合的な環境要因が多いことに気が付きます。より深い京都を知るには現地を歩く「知的な道しるべ」が必要なのです。
今回、4月より現地を教員とともに回り、以後も各グループなどで現地確認を重ねながら京都の地勢や各地の息吹を感じ、自己の旺盛な好奇心に出会いました。雨の多い時期とも重なりましたが、写真の撮り方や人々の観察、ヒヤリングや史実・資料など確かな情報にも向き合いながら演習を積み重ねました。

阿弥陀ヶ峰から鴨川まで続く傾斜地には古代から多くの権力者が施設を作りました。

桃山時代には秀吉が大仏殿を作るために鴨川のほとりからこの場所まで掘割を作り、石材や木材、金属などを運ぶ港があったのです。
正面通は山を切り、大仏を鋳造した粘土鋳型を砕いて造成された直線道路になっています。
大学の住所が上堀詰町というのはこの港を埋め立てられた江戸時代の地名であったのです。
魚屋さんや料亭もこの港に関係しているのかもしれませんね。

その情報にはアイコンのデザインをはじめ経路の記載や現地写真の添付など独自の視点を追記していきました。
また国土地理院マップ、古地図、各時代オーバーレイマップ、古写真、さらにどんどん焼けなど過去の被災エリアなどにも目を通し、
隠れた情報をあぶりだします。
この学生さんは新選組の足跡をたどりました。彼らの足跡は高瀬川に近しい場所が多いことは知られていましたが、
壬生には西高瀬川が昔流れていました。隠密行動には航行であったのでしょうか?ロマンが広がります。
現地情報を資料や教員の指摘を基に整理します。形が現れますと「テーマ設定」や「なぜこの事例を選んだのか」という難題に再度ぶつかります。センスには建築や景観の知識と感性が要求されると同時に、設計意図を紡ぎだして建築形態の裏側にある当時の時代背景や造形理念を再考する能力も要求されます。

発表に合わせてリアルタイムに情報を検索しながら、教員と学生が共にフィールドサーヴェイの結果を紡いでいきます。




最終日には素晴らしい作品が提出され、建築との対話から生まれた「京都学」が学生皆さんの中に生まれたと思います。お疲れさまでした!
(講師 北岡慎也)