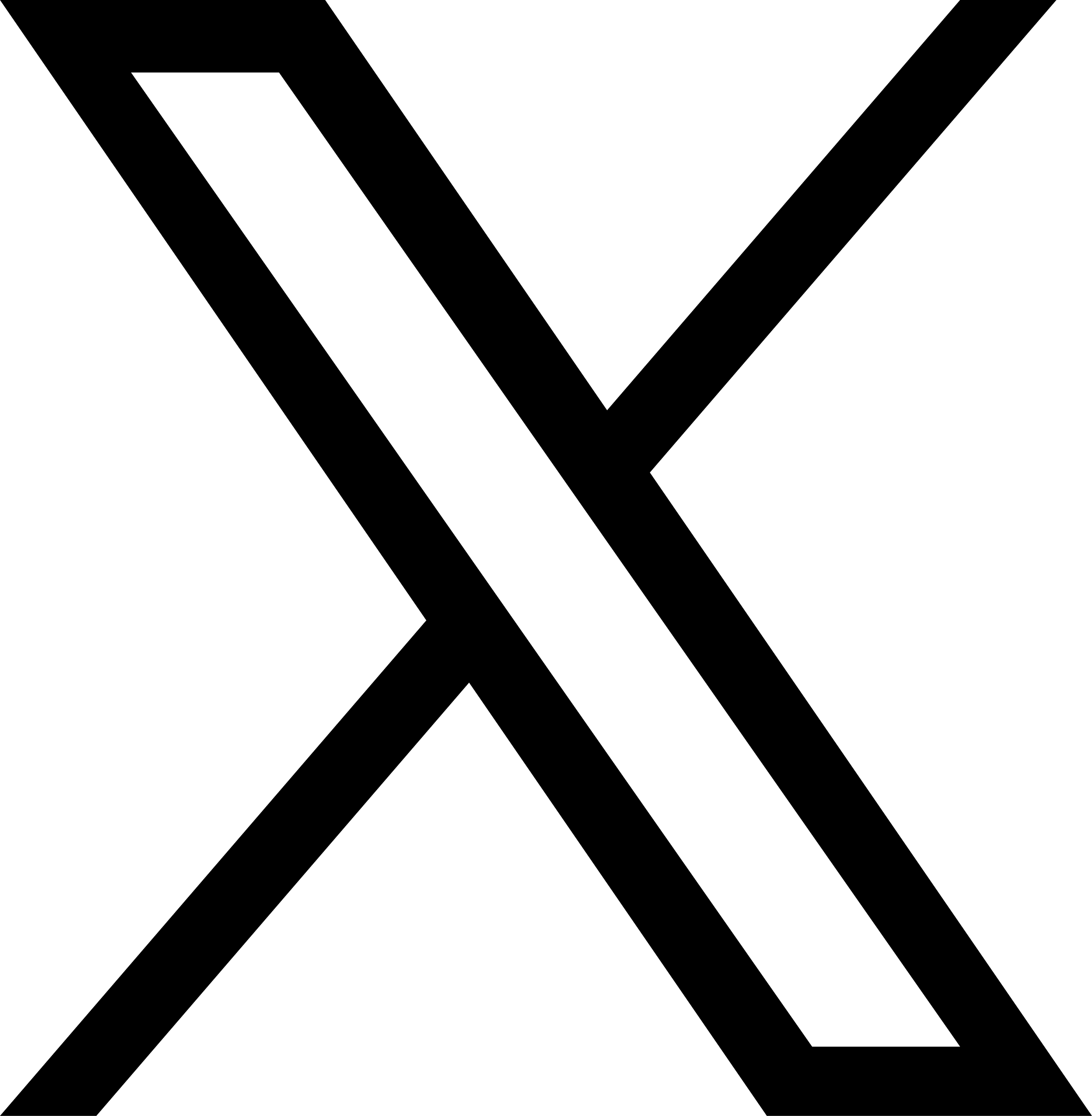建築学科2年生後期の「建築設計演習I」を紹介します。この設計演習では「集合住宅」と「保育園」の二つの設計課題が行われました。
第一課題のテーマは「交流スペースを持つ低層集合住宅」でした。敷地は京都美術工芸大学からほど近い、京都国立博物館の西側、七条通りから一筋入った大和大路通りに面しています。住戸数は15戸から30戸、階数は概ね3階以下とする設定です。敷地の調査分析、事例研究、ファーストスケッチ、ゾーニング、平面計画、断面計画と設計を進めて行きました。
中庭を持つロの字型やコの字型の配置、メゾネットタイプ(2階、3階など複数の層を持つ住戸)、細い隙間を持つものなど様々な提案がありました。歴史的な京都の街並みに対して、また、現在の都市居住や集まって住まうことに対してどのように答えていくのかがポイントであったように思います。
「おすそ分け 〜暮らしの十字路〜」では、植栽やガーデンファニチャー、洗濯物など、住民の暮らしが外部に溢れ出ることを設計に取り入れています。ご近所付き合いや人のつながりが大切にする東京や大阪の下町のような暮らし方が感じられました。外観は都市部に残る木造密集地域のような様相であり、同地域の価値をあらためて感じます。「wave roof」では、細長い平面の住戸が連続し、こちらは京都の町屋が並ぶ街区のような様相です。両者を見ていますと、昔のように隣人と関わる暮らし方に発見があることが分かります。




第二課題は「まちなかの保育園」がテーマでした。敷地は七条通りから高瀬川沿いに少し北上した場所にあり、大通りである河原町通りと高瀬川沿いの小さな通りに面しています。この課題では、周辺環境を読み解きながら保育園としての機能をまとめ、園児たちが豊かな時間を過ごせることを考えながら設計を進めていきました。また、地域との関わり方を提案する必要がありました。構造は鉄筋コンクリートのラーメン構造とする課題条件であり、同構造を理解することも課題の目的の一つでした。
ここでは2つの設計制作を紹介します。「想像力が広がる保育園」では、滑り台や鉄棒、小屋やビオトープなど遊びに要素を積極的に設計に取り入れ、園児たちの遊びの活動を誘発することを提案しています。「オオキナ保育園」は、1階、地下階、屋上テラスなど、園の内部を積極的に地域に開放し、地域と保育園の一体化を目指す提案です。どちらの案も屋上を有効活用し、限られた敷地の中で外のアクティビティのスペースを確保しています。小さなボリュームによる構成は高瀬川沿いの街並みに調和しそうです。
2年生の後期から課題の規模が大きくなっていきますし、諸室の配置や構造を適切に解きながら、社会や地域といったに広い視野を持つことが必要になってきます。一つ一つの設計課題が皆さんの設計の力を培ってくれています。次の課題も頑張りましょう。




一方、第ニ課題の期間に伝統建築領域では「伏見稲荷大社本殿の模型制作」を行っています。同建築物は伏見稲荷大社の本殿であり、明応3年(1494)年に建立され、京都市内では現存する最古の社殿です。国指定重要文化財であり、五間社流造という形式に特徴があります。現地見学を行い、実物を見てから模型を制作しています。縮尺は1/20であり、ヒノキ棒やバルサ材などの木質系の材料で制作しています。5つのグループに分かれ、部位ごとに制作を行います。完成が近づいたら各部位を接合します。今年度は彩色を行うとのことであり、より実物に近しく再現される予定です。とても楽しみですね。
(准教授 白鳥洋子)