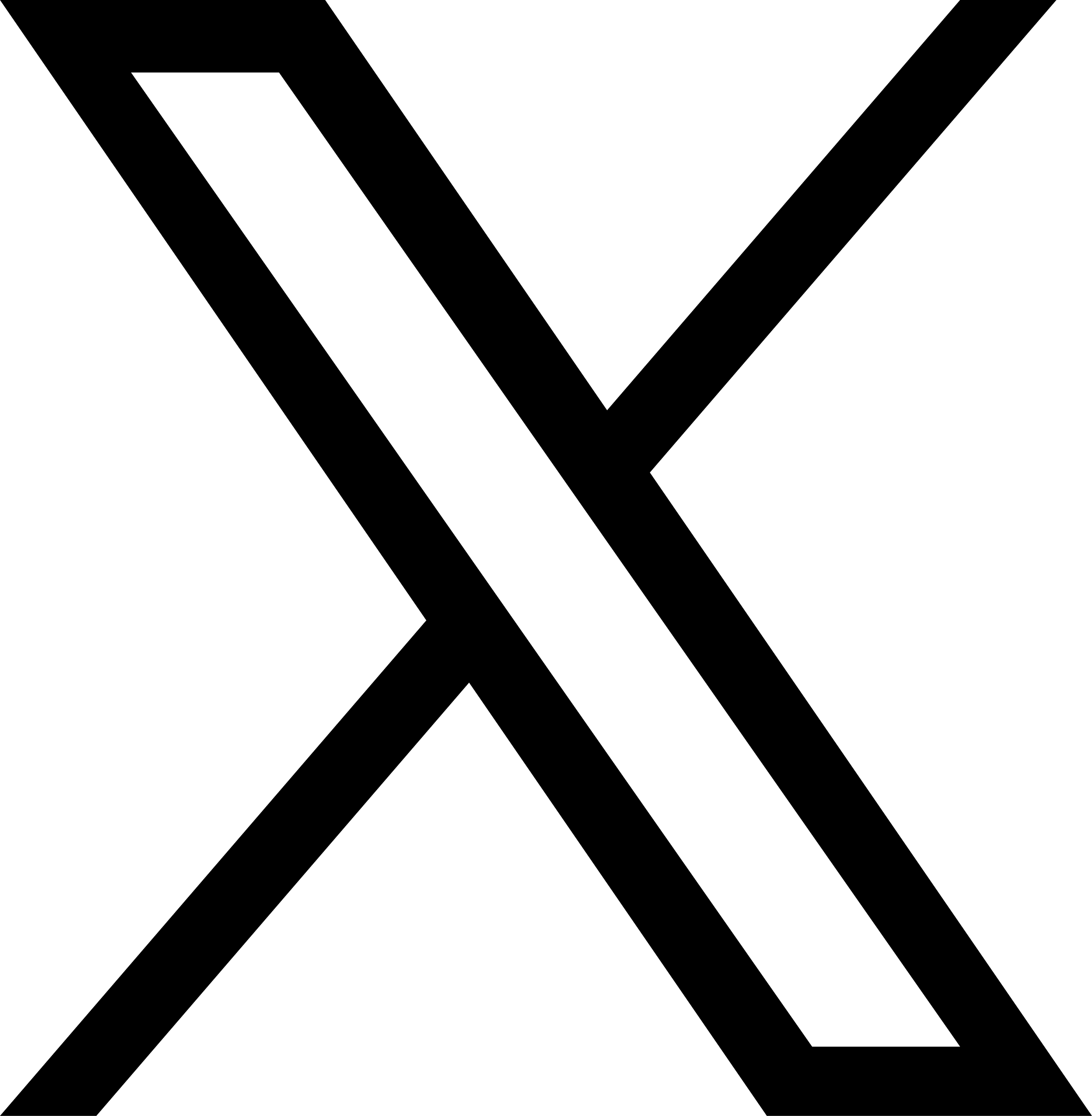文化財コースでは、3年生になると専門実習で仏像修復を行っています。
本年度は南丹市の三十三観音のうち「千手観音」と「如意輪観音」の2体で、江戸時代の御像です。千手観音班と如意輪観音班の2班に分かれてそれぞれ作業を行います。

文化財の修復は、基本は現状維持修復です。あるままを残す、これが最も重要です。
修復の大きな流れとしては以下の通りです。
損傷状態の調査→修理前写真の撮影→クリーニング→彩色層剝落止め→解体→解体写真→接着→新補→補彩→完成写真撮影→報告書
御像の状態によって作業の増減はありますが、仲間と協力して臨機応変に対応していきます。
今回は上記の手順のうち、解体及び剥落止めの様子をお届けいたします。
初めての経験であるため、学生からも緊張の色がうかがえます。


さて、如意輪観音は、御像が半跏する台座の損傷が激しく、今にも倒壊しそうな状態でした。
そこで今回は台座の全解体を行います。解体を行う前に欠かせないのが剥落止めです。
制作から300年以上経過した本像は、彩色や金箔を留める接着剤が劣化しており、その剥落を防ぐために行うのが剥落止めです。膠とふのりを混ぜた粘度の低い接着剤を使用し、しっかりと木地に定着させていきます。
漆層の保護の為に、典具帖紙という薄い和紙を貼り付けます。

保護が出来たらいよいよ解体です。モノを傷つけないように慎重に取り外していきます。

一方の千手観音は、台座と千手観音像の脇手と呼ばれる沢山の腕を解体しています。
1つ1つ丁寧に取り外していきます。

解体終了後は、解体写真の撮影、新補、接着と作業は続いていきます。
完成が楽しみです。
特任教授 小林泰弘