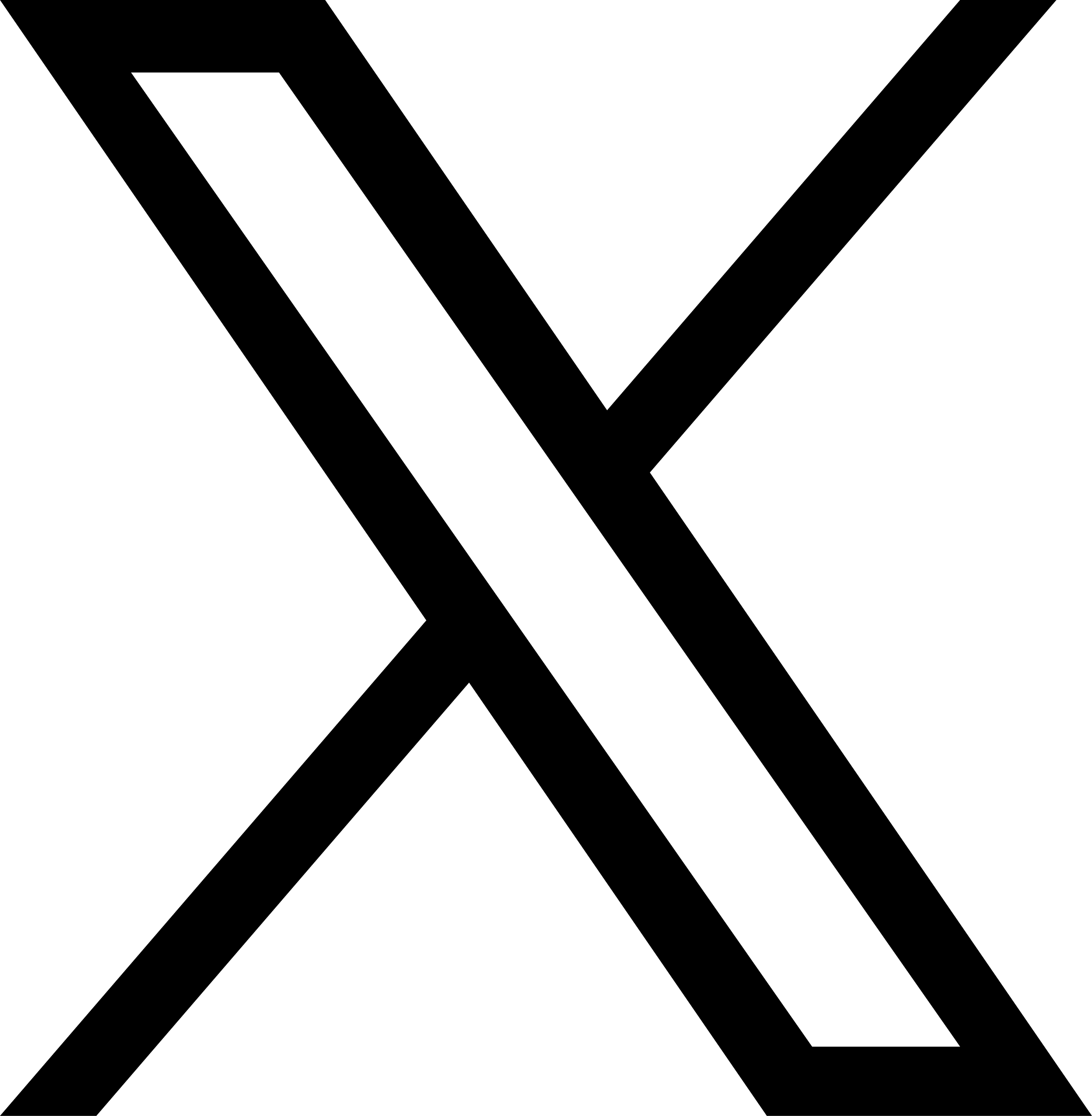皆さんこんにちは。
工芸領域の教員、遠藤です。専門は漆工芸です。
今回は夏休み期間中に2日間にわたって開講された、集中講義の「構成基礎演習」についてご紹介いたします。

この演習では陶磁器片を接合して、自身のアイデアを活かした、ちょっとしたオブジェを作りました。ここでは
1 簡単な金継(きんつぎ)の作業を体験する。
2 普段の実習では扱わない合成樹脂素材などを使ってみる。
3 ある素材を別の用途に流用して再構成してみる。
という3点がテーマとして設定されています。対象は工芸領域1年生の受講希望者ですが、木工・彫刻、陶芸、漆芸の学生が一緒に学んでいます。


それでは工程を順を追って見てゆきましょう。どのような作品ができあがったのでしょうか?


まず始めに作品に使う陶磁器片を選びます。


陶磁器片は陶芸の川尻先生・守崎先生にご提供いただきました。ありがとうございました。


自分の作品のイメージに合うものを選んだり、陶磁器片の色や形から作るものをイメージしたり
と様々です。
作りたい作品のイメージが固まったら破片を接合していきます。
接着には合成素材のエポキシ系接着剤を使用しました。
本来なら、漆を接着剤や穴埋めの充填材として使いますがさまざまな素材に触れる経験のため今回は合成の素材です。

主剤と硬化剤をよく練り、混ぜ合わせます。


破片の隙間に流し込んだり、断面(接着面)に適量付けて破片を貼り合わせます。

接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきます。


接着剤が硬化したら、破片の隙間をパテで埋めていきます。今回はエポキシ系のパテを使いました。


パテが足りなくなりそうでしたので、大きな隙間はエポキシ接着剤に木の粉ノコギリの挽き粉)を混ぜたものも使っています。
接着の効果もありますので、一石二鳥ですね。
ここまでで1日目は終了です。
2日目です。 1日目に接合部分の穴を埋めたパテが硬化しています。

硬化したパテの表面を#240と#400の紙ヤスリを使って研いで均します。
陶磁器表面にキズをつけないように注意が必要です。

パテ表面の凹凸の状態によっては彫刻刀も使って削ります。


パテ埋め箇所の形が整ったら、カシュ―塗料をやや厚めに塗ります。
ムラにならないように気をつけましょう。


カシュ―がやや乾いたタイミングで、真鍮(しんちゅう:黄銅)の粉を毛棒(けぼう)という
筆のような道具で継ぎ目の箇所にのせていきます。

今回は初めての体験ということで真鍮粉を使いました。
本式の金継は金粉、場合により銀粉を使います。
3年次の演習で学ぶ機会があります。
カシュ―が乾いたら、陶磁器面に付いた不要な真鍮粉を取り除いて完成です。
それでは完成した作品を見てゆきましょう。









鳥やウサギ、舟形などもありますね。形や色の組み合わせなどなかなか面白いものができたのではないでしょうか?
後期以降も学生の皆さんは専攻している工芸についてより深めていくことになりますね。
今回の経験をこれからに活かしていただきたいと思います。