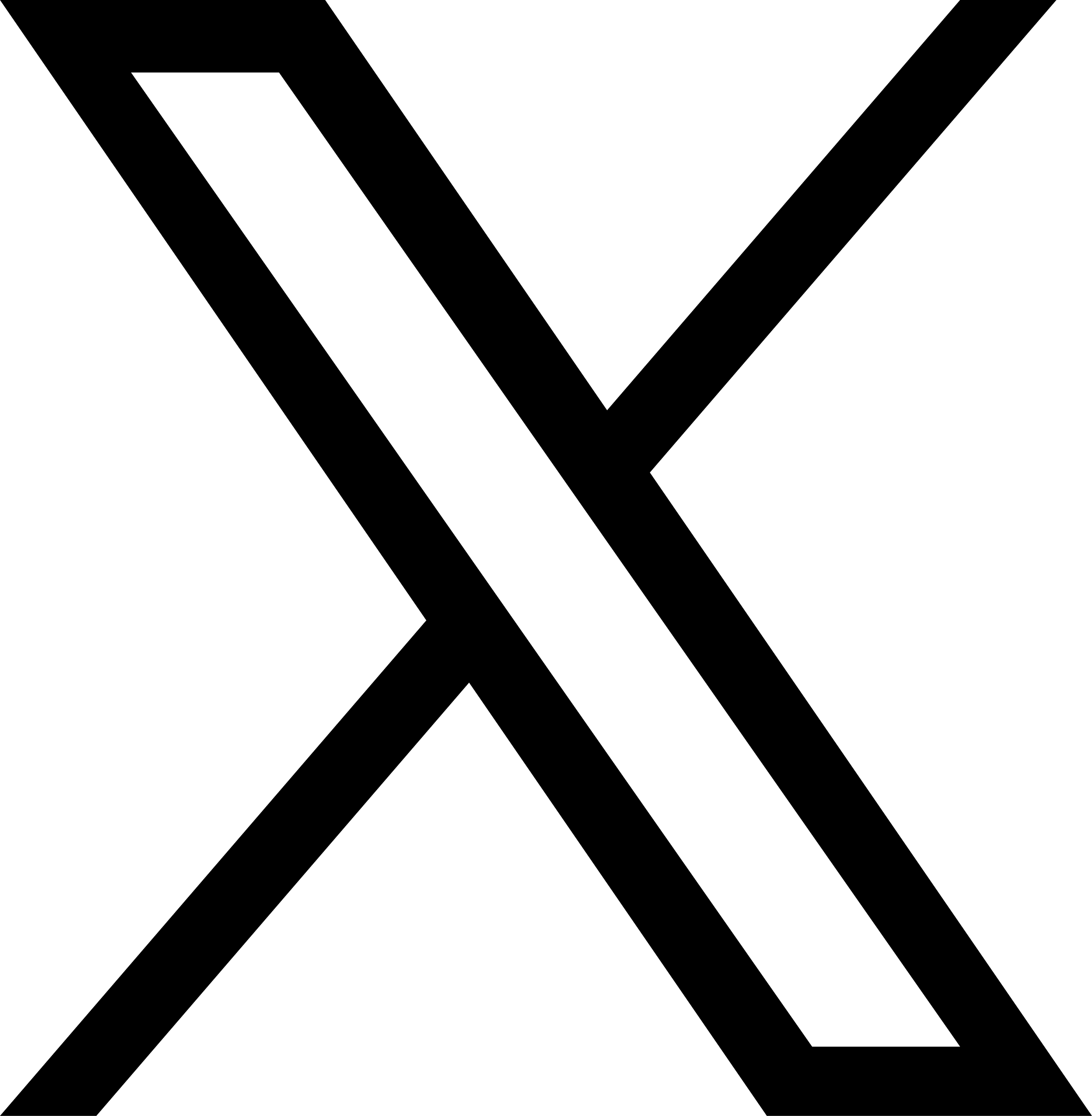みなさんこんにちは。
工芸領域教員・漆芸の遠藤です。
漆の工芸品には、貝の真珠層を模様状に加工した
「螺鈿(らでん)」という加飾(飾り付け)の技法があります。
この技法では、夜光貝・蝶貝・鮑貝などが使われていますが
貝の真珠層から反射されて目に入る
青や緑、ピンクいろなどのいわゆる構造色が大変美しく
1000年以上の昔から、見る者を引き付けて止まない魅力があります。

一般に私たちが作品を作る場合
漆芸の材料を扱うお店から、素材として加工された貝の板を購入
表現したい模様に切り抜いて作品上に漆で貼り付けます。
ちょっと寄り道をしますが
過去の実習で作業していた「厚貝(あつがい)」の技法について
少し見てみましょう。

初めに図案の輪郭を貝に写して、糸鋸で切り出します。

次に輪郭線をやすりで削って整えます。

板に仮止めして、表面を紙やすりできれいに整え
研磨剤でこすって光沢を付けます。

最後に作品の表面に漆で貼り付けて完成です。

厚貝の技法には、表面に貼り付けるだけでなく
作品を彫り込んで嵌め込む方法もあります。

こちらの方が難易度は高いかもしれません。
さて、今回の演習では
必ずしも漆芸の螺鈿技法を学ぶ、ということではなく
漆芸以外の学生それぞれが所属する専攻で
普段あまり出てこない「貝」という素材を使い
加工して作品を作ってみることを目標にしています。
貝を使った作品を考え、使えそうな貝を探し
実際に加工して形にしてゆくところがポイントです。
貝の入手方法は、購入・採集・譲り受ける
どれでも構いません。

さっそく貝を手に入れてきました。魚屋さんで購入したそうです。
何やら茹でているようですが・・・・

この後、おいしくいただきました。安全なものであれば
賞味することで素材への理解も深まりますので
作品をイメージする上で、実は大切なことかもしれませんね。

手に入れた貝殻を使えるようにしてゆきます。
場合によっては「塩抜き」が必要になります。
茹でてみたり、長期間水に浸けたりと
なかなか手間がかかります。


ある動画サイトで見つけた方法を試してみます。
塩酸系の洗剤で貝殻の外殻を溶かして
内側の真珠層を出せるか実験しました。
素手ではあまり良くありませんので
安全面を配慮して手袋を着用します。

しばらく洗剤に浸けた後、表面を金属ブラシでこすって外殻を剥がしてゆきます。

かなり真珠層が見えてきました。
外殻の落ちがもう一つのところは、綿棒なども活用して
ピンポイントで剥がしてゆきます。

物理的手段で外殻を除去する学生もいます。やすりで削っていますね。

漆芸の螺鈿では使わない貝にもチャレンジです。
学生それぞれのアイデア・目の付けどころが面白いですね。

ある程度イメージが固まり、貝の準備ができましたので、試作してみます。
透明な合成樹脂に絵の具を混ぜ、色を付けています。

貝の中に海があるような、面白い作品ができました。小さな巻貝が見えますね。

こちらの作品では、光硬化樹脂に専用の染料で色を付け
線描き蒔絵の模様に被せています。

光硬化樹脂を固めています。
まだ前期の途中ですので、授業は残り5週間ほど残っています。
これからますます
オリジナリティあふれる作品が出来あがってくると思います。
つい先日の授業で学生諸君には
作品の進み具合や今後の展開について
授業内で簡単な発表をしてもらいました。
作品はアクセサリーが多いようですね。
他の人に話すことで、自分のアイデアや
これからの工程を改めて把握することにもなりますね。

それでは学生の皆さん、楽しい作品を期待しています。