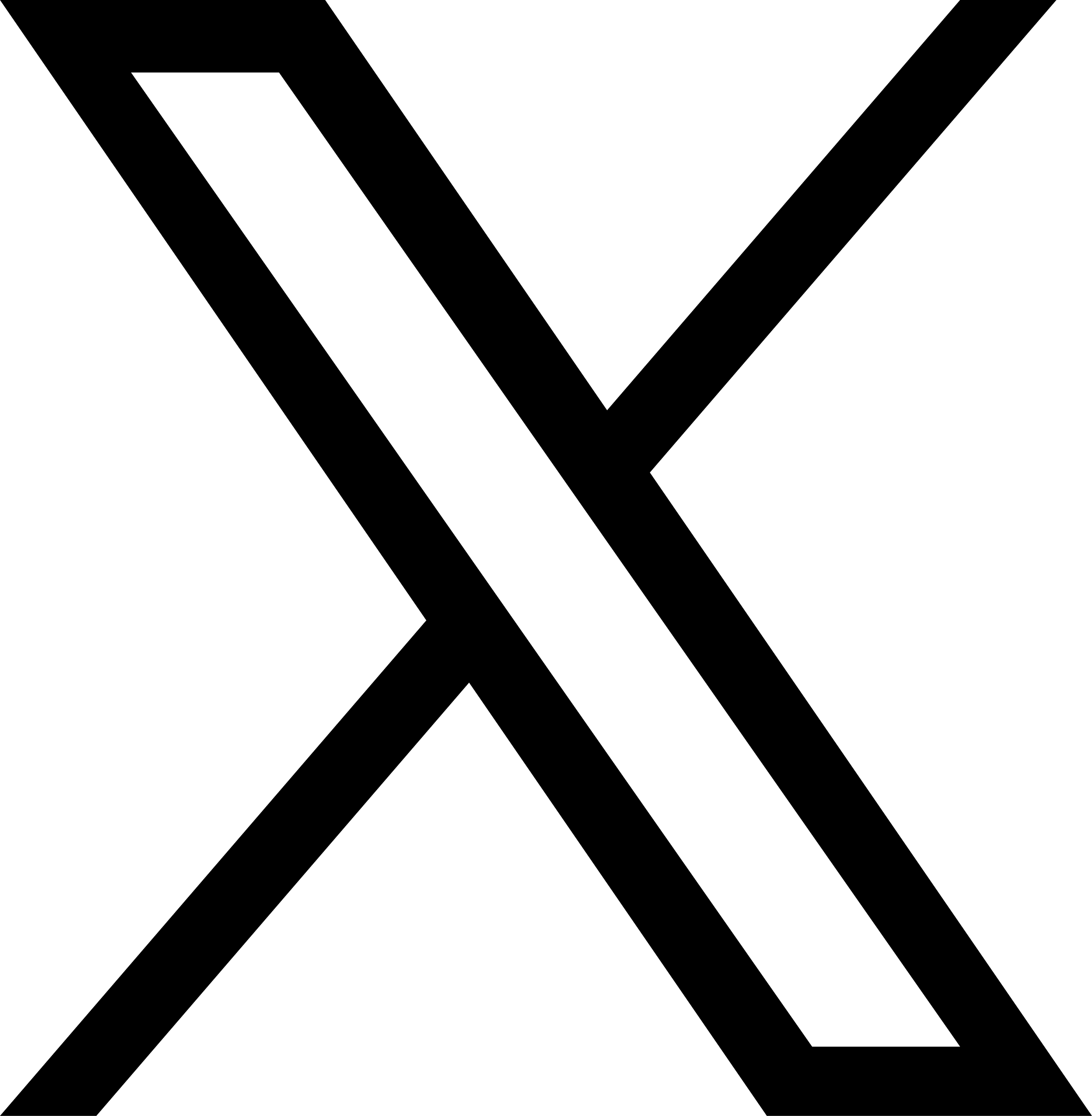7月19日(金)、祇園祭の山鉾のひとつ「鷹山」の大屋根の実測を行いました。

現在、巡行に加列しなくなってから約190年を経て復帰した「鷹山」の彫刻新調プロジェクトを、芸術学部の学生有志6名が参加して進めています。屋根の破風板部分に付ける懸魚(げぎょ)と棟の両端に置く獅子口(ししぐち)の鰭(ひれ)のデザインの考案、下図制作などに取り組む予定です。






今回の実測はその事前調査にあたり、7月24日(日)の後祭巡行に向けて山を組み上げるタイミングで屋根に上らせていただきました。学生たちは建築学部伝統建築領域の井上年和准教授の指導の下、慎重に実測していました。
今後もプロジェクトの進捗を随時公開して参ります。


〈「鷹山」について〉
応仁の乱以前より「鷹つかい山」として巡行した山鉾のひとつである。 江戸時代に曳山となり、天明の大火で罹災、寛政年間に現在の「北観音山・南観音山」と同様の大屋根を持つ曳山として復活したが、文政年間に大風雨により大破し、巡行を取りやめた。その後復活を果たせず、幕末の蛤御門の変にて大半の部材が焼失。ただ、人形3体は焼失を免れ、後祭の宵山に居祭として、木彫の「鷹」「犬」と共にお町内にてお飾りを続行。復興を目指して令和元年(2019)より唐櫃巡行(からびつじゅんこう)に加わり、令和4年(2022)、196年ぶりに巡行復帰を果たした。(祇園祭山鉾連合会ホームページより抜粋)