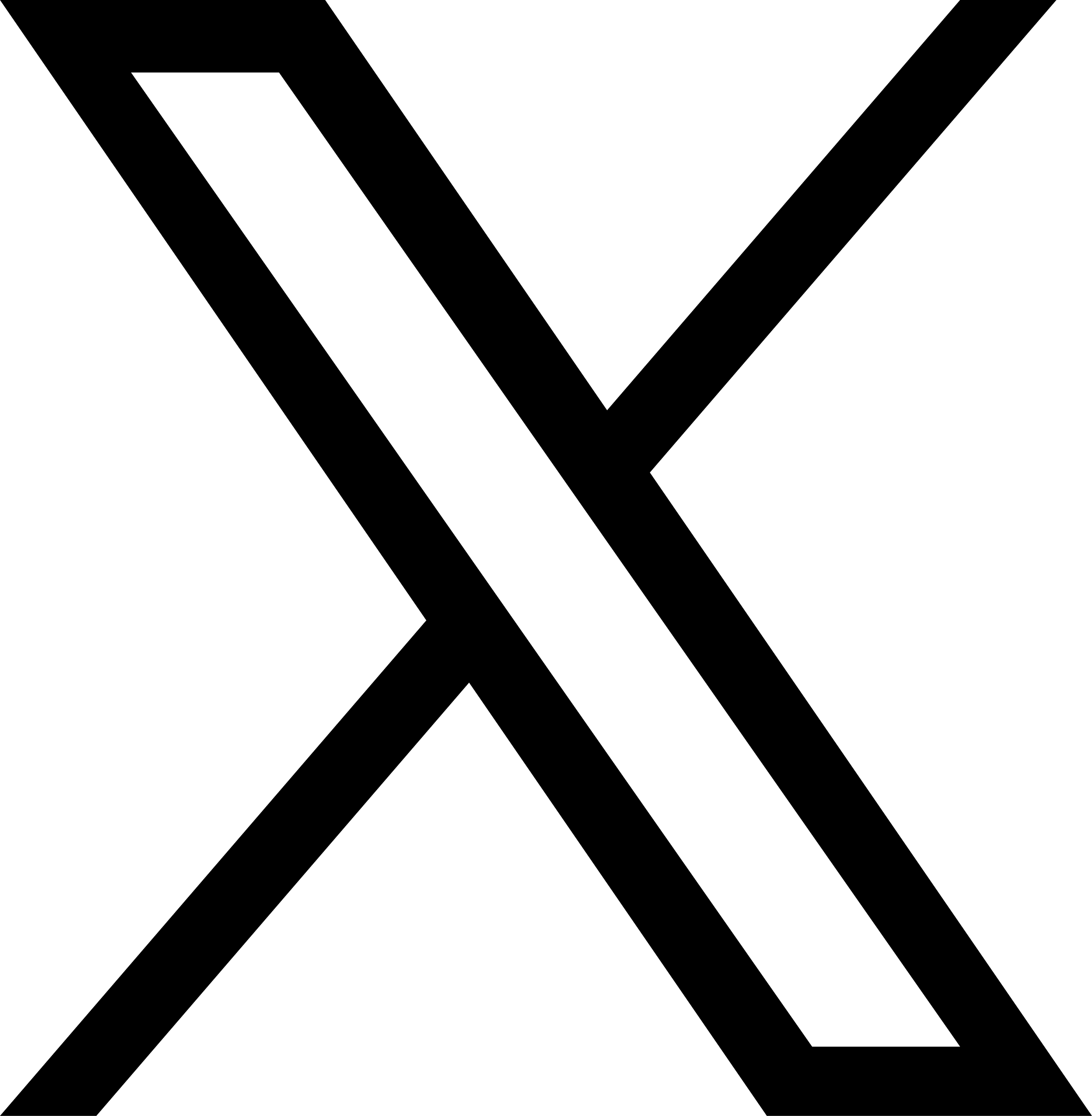3月1日(土)、京都伝統工芸館で開催中の企画展「技と知の交差点-正倉院宝物復元プロジェクトの歩みー」関連イベント・シンポジウム「正倉院宝物復元の舞台裏-復元された技と知-」が実施され、約70名の方が参加されました。

正倉院宝物は、奈良時代に東大寺を造立した聖武天皇の遺愛品を光明皇后が大仏に献納したことに端を発し、当時の伝統工芸の粋を約1300年の時を経て伝える世界的にも稀有な文化財です。
本学では、その正倉院宝物の一部を復元模造する「正倉院宝物復元プロジェクト」に、開学以来9年にわたり取り組んできました。このたびの展覧会では同プロジェクトで制作された復元作品とその制作プロセスを紹介しています。



シンポジウムは宮内庁正倉院事務所前所長・⻄川 明彦氏の基調講演からスタート。
そもそも「何のために模造するのか」という根本的なところから、いま模造する意味や「模造する宝物はどのように選ぶのか」といったことについて、正倉院の現場に勤められる方しかご存じない具体的な例を交えてお話しくださいました。


続いて、「正倉院宝物復元プロジェクト」で指導にあたられた村上 隆特任教授(⾼岡市美術館 館⻑)と⼩林 泰弘特任教授(環⽂化財修復⼯房 代表)、復元作品の制作にあたった1期生・⼀⼾ 葉⾳氏(南丹市教育委員会)と5期生・夛⽥ 瑠璃⼦氏(株式会社 さわの道⽞)も登壇され、古閑 謙太郎助教の司会進行により、制作当時の様子を詳しく紹介されました。


各年度に復元する作品は約9000件もある正倉院宝物から学生たち自身が選定し、現物を実際に見ることはできないため調査資料を読み解くことから始め、材料の調達も自分たちで行い、夏期休暇も冬期休暇も返上して約1年かけて完成させていたそうです。実際に取り組んだ卒業生たちのお話からは、制作現場の苦労や楽しさがありありと伝わってきました。


そしてその出来栄えについて、正倉院事務所で行われているプロの工芸家による模造とはまた異なる学生による復元ならではの魅力があり、正倉院宝物の多くが制作された天平時代の大らかさを纏うものと、先生方からご高評を仰ぎました。
今回のシンポジウムを通して、3Dプリンターなどの技術がどんなに進歩しても人の手わざなくしてはつくることができない伝統工芸の魅力、文化財を守り伝えることの大切さが強く感じられました。
展覧会は3月30日(日)まで開催しています。若い力によって貴重な文化財を未来へと繋ぐプロジェクトの全貌を、ぜひ会場でご覧ください。
【展覧会概要】
会場|京都伝統工芸館 5階展示場
会期|2025 年 2 ⽉ 28 ⽇(金) 〜3 ⽉ 30 ⽇(日)
開館時間|10:00 – 17:30(入館は17:00まで)
休館日|火曜日・水曜日
入館料|⼤⼈・⼤学⽣:500 円
(コンソーシアム京都に加盟されている⼤学の⼤学⽣は 100 円)
シニア(65 歳以上の⽅)・和服を着⽤の⽅ :400 円
⾝体の不⾃由な⽅・⾼校⽣以下:無料
主催|京都美術⼯芸⼤学 芸術学部 デザイン・⼯芸学科 ⽂化財情報デザインコース
協力|株式会社 タカムラ産業